発展途上国に旅行に行く人が気をつけるべき病気の1つが「狂犬病」になります。今回は動物の雑学の中でも予防と対策と言うべき議題を挙げていきたいと思います。
【狂犬病の予防と対策】噛まれたら致死率ほぼ100%の恐怖
渡航する前、移住する前に予防接種する方もいると思います。実際に犬に噛まれて急遽ワクチン接種をすることになった人も見受けられます。
1950年代から日本国内での狂犬病発症は0%になります。何故なら犬に予防接種しているのと犬を登録し、さらに殺処分や、狂犬病の予防接種をしているからになります。
そのおかげで日本が狂犬病洗浄地域だからです。世界的に狂犬病はかなり致死性の高い病気になります。
・実は犬に噛まれただけでは致死率100%にはなりません。噛まれた後に適切な処置をしていれば発症を止めることができます。
噛まれて狂犬病が発症してしまった時点で100%の致死率になります。
だからほぼ100%の致死率と考えられます。
狂犬病はオーストラリア、ニュージーランド、アイスランド、日本など一部の地域を除く世界のあらゆる地域で発生しています。(何故オーストラリア、ニュージーランド、アイスランド、日本で発生していないかは後で書いておきます。)
下図出展:厚生労働省HP

狂犬病は狂犬病ウイルスによって引き起こされ、人が発症すれば致死率はほぼ100%です。助かった例もごくわずかにありますが、非常に幸運な例です。死亡者数は年間5万5千人と言われています。
【狂犬病の予防と対策】意識と一次処置
海外で犬に噛まれた時どうしたら良いのかよくわからない人が多いと思います。一応私の看護師の視点と厚生労働省のホームページからの情報も載せていきます。
看護師の視点では一次処置として清潔な水と石鹸でよく流します。この時に傷口を出血させるようにすると効果的になります。(狂犬病の感染キャリアは唾液のため唾液を洗い流す意味があります。)針刺しの暴露の場合も同じ行動をとります。
そしてすぐに医療機関に行って初めのワクチンを打ってもらう事が必要になります。海外での受賞の場合は検疫所に報告も必要になります。

【狂犬病の予防と対策】犬からの感染だけではない。
ご存知だと思いますが、狂犬病は狂犬病ウイルスに感染したイヌに噛まれることによって人に感染します。
実は狂犬病ウイルスはイヌだけでなく、ネコやコウモリなども持っています。
下図出展:厚生労働省HP
【狂犬病の予防と対策】狂犬病の病態・症状・特徴
症状と特徴
狂犬病ウイルスは、傷口から体内に入り込み、神経を伝ってゆっくりと脳へ向かいます。そして、脳に到達すると一気に増殖をはじめ、脳細胞を破壊しながら人を死へと追い込みます。
発症すると、まず強い不安感や錯乱が現れ、やがて「水を飲むのが怖くなる(恐水症)」という異常な症状が出ます。次第に高熱や麻痺、全身のけいれんが起こり、最終的には呼吸ができなくなり、ほぼ確実に死亡します。
しかし、このウイルスは脳に達するまで増殖しないため、感染していても発症するまでは検査で見つけることができません。つまり、「本当に感染しているか」は誰にもわからないのです。
唯一の助かる道は、「発症する前」にワクチンを打つこと。しかし、発症してしまったら現在狂犬病脳症に効く薬はないのです。
NIID国立感染症研究所の発表で2020年に国内に入ってきてしまった事例を挙げています。このことはまた後で追記いたします。NIID事例
噛まれたらすぐに病院へ――それが自分や家族の命を守る唯一の方法になります。
・噛まれたら、感染しているしていない関わらず、ワクチンの接種が必要になります。
・ワクチンの接種をしていても噛まれたらワクチンの接種が必要となる。
注意:見逃されている事例では噛まれれも出血がなかったり、皮下組織まで傷が届いてなかったから放置したなどがあります。
実は狂犬病の感染は噛まれなくても傷口に唾液が入ったら感染します。狂犬病の感染は人から人への輸血などでは感染の報告が上がったという報告はありません。
唾液が傷口に入ったからと言うことになります。
噛まれてから発症する期間は?
教科書的には発症までに1ヶ月~3ヶ月ほどかかることが書かれています。しかし症例によっては1年以上経ってからの発症、もっと短い症例もあるのであくまで目安として考えてください。
発症までの時間は当然噛まれた部位、ワクチン接種歴に影響を受けることがわかっています。
そうなると犬に噛まれた場所が脳から遠ければ遠いほど、発症までには時間がかかると考えられており、事前にワクチンを接種したことがあれば、発症を完全に防ぐことはできないが、狂犬病の病状発症までの期間を伸ばすことができるのです。
【狂犬病の予防と対策】狂犬病対策
海外旅行にワクチンは必要か?
狂犬病はワクチンが有効なのがわかっています。それは日本の防疫がしっかりしており、国内に狂犬病が入らないようにしているのと、事前に犬に感染しないように輸入犬の防疫や国内の犬の防疫をしっかりしていることからわかります。
狂犬病の抗体を体内に作り上げるには3回の接種が必要です。日本国内生産されたラビピュール・ワクチンサイトからの抜粋です。
曝露後:受傷当日、3日、7日、14日、28日目 筋肉内接種(5回接種)
他のサイトではワクチン接種は1回目から3回目まで6ヶ月など書いてありますがそれは時間が経ち、古い情報になります。国立国際医療研究センター病院HPでもワクチンサイトと同じ使用の仕方を指示しています。
4 回接種:0(接種部位を変えて、2 箇所に 1 回ずつ、計 2 回)、7、21 日
5 回接種:0、3、7、14、28 日
6 回接種: 0、3、7、14、30、90 日

- 事前に3回接種&最後の接種から6ヶ月以内
- 噛まれたあとに2回の追加接種が必要
- 発症するリスクは低くなり、発症までの期間も延長する
- 事前に1回、2回接種もしくは3回目接種から6ヶ月経過
- 噛まれたら6回のワクチン接種が必要
- 発症までの期間はワクチン回数が多いほうが延長すると考えられる。(病院にはすぐに行きましょう)
- 事前にワクチンなし
- 噛まれたら6回のワクチン接種が必要
- 噛まれたらすぐに病院へいく必要あり。
他のHPからの情報です。他のHPでは上記のように書かれていますが、まずは噛まれたら最寄りの医療機関に相談してください。
それと私は看護師なのでこの狂犬病のワクチンは国立国際医療研究センター病院HPに書かれているように1本12000円もの薬自体の値段がかかります。これに
病院までのアクセスが困難な人や噛まれるリスクが高い人はしっかり3回摂取するべきだと思います。ただ費用も一回1万円以上かかるので、普通の旅行をする人はあまり打っていないのが現状だと思います。噛まれたらしっかり病院にいくことが前提ですが。
ただ、噛んだイヌを観察できれば、このイヌがその後ピンピンしていれば、暴露後の接種はやめて大丈夫です。WHOのガイドラインでも言われています。
噛まれないために
まずは不用意に動物に近づかないことが大切です。先ほど書きましたが、狂犬病はイヌだけでなく、ネコやコウモリ・アライグマや野生動物にも宿主となります。
なのでネコだから安心と考えている時点でアウトになります。猫は手を舐めています。爪に狂犬病ウイルスがいた場合引っかかれただけで痛い目に遭います。なので海外で野良ネコを触ろうとすることはやめてください。
日本国内の発生している狂犬病のほとんどのケースではイヌから人に感染しています。海外でも犬からの感染が多いようです。
特にイヌには警戒する必要があります。近年コロナが蔓延した時のように見分けは絶対つかないのはお分かりだと思います。
なので狂犬病を発症している犬とそうでないいぬと見分けするのが難しいです。
狂犬病の名の通り犬が狂犬になることもないからです。犬が狂犬病に感染したから必ずしも犬が凶暴になるわけではないからです。
元気がなくなるものもいるからです。教科書的には狂騒型が7割、麻痺型は3割と言われています。まあしょんぼりしたイヌにちょっかいかけて噛まれた、なんて人はもう知りません。ちなみに麻痺型は後半身から麻痺するため、足腰の立たないイヌがいたら一応気をつけましょう。
噛まれたけど、このイヌなら大丈夫そう?
大体の人は元気イヌに噛まれたけど、これが狂犬病のせいなのか、ただの元気なイヌなのかどっちなんだ!というケースで悩まれるでしょう。まあ病院に行くのが一番です。命を失っても病院にいけない事情がある、そんなアンダーグラウンドを生きるあなたのために、判断基準をアドバイスするとしたら、「噛んだイヌが10日後も元気に生きている」場合、これは狂犬病を発症していません。ただ、野良イヌを観察し続けるのは厳しいですね。また狂犬病を発症して凶暴になっているイヌは絶えず吠え続けていることが多く、よだれを垂れ流しています。
- ずっと吠えており、落ち着きのないイヌに噛まれた。(危険度1)
- イヌの口の周りに泡沫状の泡もしくは、よだれダラダラ (危険度2)
- イヌが水を避けている (危険度3)
- 数日後イヌが死んでいた。(驚きのヤバさ)
です。危険度を書きましたが、実際はすべて危険度MAX近づくなと言う事です。もう一度言いますがイヌを観察している暇があったら病院に行きましょう。
狂犬病の予防接種の情報
| 予防できる病気 | 狂犬病 |
| ワクチンの種類 | 不活化ワクチン |
| 定期/任意/保険適用/輸入 | 任意接種(国産)
以下の場合においては保険が適用される 輸入ワクチン:自費 |
| 接種回数 | *「曝露」とは「受傷」のことです
曝露前(事前予防)のため:(2~)3回 曝露後(発症阻止)のため:4回〜6回 |
| 接種量 | ラビピュール® : 1.0mL VERORAB®: 0.5mL |
| 接種間隔 | 曝露前:1週間間隔で2回、更に1回目から21~28日目に1回 筋肉内接種(3回接種) 曝露後:受傷当日、3日、7日、14日、28日目 筋肉内接種(5回接種) |
| 費用※ | 1回約15,000円(施設により異なる) |
オーストラリアでは予防接種がある
オーストラリアには狂犬病はありませんが、コウモリを介して感染する「オーストラリア・リッサウイルス感染症」が存在します。このウイルスは狂犬病と似た症状を引き起こし、発症すると致死率が極めて高い病気です。特に病気やケガをしたコウモリはウイルスを持っている可能性が高く、噛まれることで人に感染することがあります。
実際に、1996年以降オーストラリアで3人が感染して死亡しています。人を襲うことはほとんどありませんが、負傷したコウモリを助けようとして噛まれるケースが報告されています。感染の疑いがある場合、発症前に狂犬病ワクチンと狂犬病用免疫グロブリンの投与が必要です。ブリスベンの救急機関や公衆衛生機関ではこれらの治療が可能です。
コウモリから犬や猫に感染することはありますが、そこから人にうつったケースは確認されていません。そのため、狂犬病ワクチンは、感染リスクの高い地域に行く人やコウモリと頻繁に接触する可能性のある人にのみ推奨されています。
まとめ
- 海外旅行時には不用意に動物に近づいてはいけない。
- 発展途上国でイヌに噛まれたときには浅い、深いひどいひどくない関係なく医療機関へ行く。
- 病院がない地域に行く場合は狂犬病のワクチンを接種してできるだけ早く行って早く帰ってきましょう。



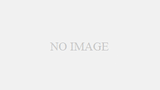
コメント